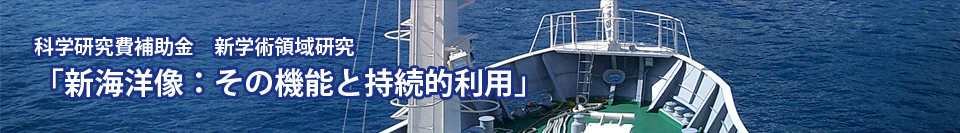連載
「文理融合」のコツII(東京大学大気海洋研究所 津田 敦)
黒倉さんのエッセイを受けて何か書けという要請がきた。黒倉さんのエッセイ「文理融合のコツ」には、コツは書いていない。社会科学と自然科学の視点の違い、方法論の違いを経験に基づいて整理している。コツは自分で考えろということだろう。
このプロジェクト「新海洋像」は、文理融合を一つの目玉として走り始めたが、文理融合自体はかなり前からあったコンセプトであり、例えば総合地球環境研究所などは、まさに、このコンセプトの具現化である。しかし、黒倉さんが指摘するように双方の文化は単純な対話では埋められない溝があり、その醸成にはコツと時間が必要であったと考えられる。しかし、この10年、身の回りで、無関係ではいられないという出来事が多くあった。2001‐2004年に行った海洋鉄散布実験は、地球工学的手法の検証という意味合いもあったが、ほとんどの参加者は自然科学における純粋な興味から実験に加わった。しかし、2006年以降状況は変わり、鉄散布実験を含む現場型海洋操作実験は、海洋投棄を規制する国際条約であるロンドン条約によって、基本的には禁止され、その実行には国際的に取り決められたプロトコルに則った公的機関による審査が必要になった。このような時代の趨勢のなかで、国際法を専門とする法学者との議論する場面も多くあり、条約にも目を通したがほとんど理解できなった。まさか純粋に自然科学的な興味から出発した実験で、このような問題に直面するとは研究開始当時は想像できなかった。さらに、ごく普通の調査航海においても、他国のEEZ内で観測する場合は相手国への申請・許可が必要であり、近年その許可を得ることが、次第に難しくなってきた。また、生物多様性条約においてABS(Access to genetic resources and Benefit Sharing)が議論され、多くの国で国益を守るための国内法が整備され始め、採水や微小生物の採集においてもEEZクリアランスに加え各国の国内法に準じた申請と許可が必要になってきた。すなわち、ごく一般的に行われている海洋観測においても国際法に準じた多くの手続きを踏むことになり、その情勢は刻一刻と変化し、我々が、それらに関して無知でいることが困難になってきている。さらに、海洋鉄散布が実験の域を超え地球工学手法の実施段階になると、実験において、その有効性が「科学的」に証明できたとしても、その実行には法的な問題も含めた国際的合意形成、利益や損害の再配分など、問題の解決には自然科学の枠を超えたプロセスが、とても超えられそうに見えない壁として立ちはだかっている。
一方、いわゆる文理融合型科学も身近なものになりつつある。過去において参加した総合地球環境研究所の「アムール・オホーツクプロジェクト」では、アムール川上流の森林によって生物が利用可能な鉄分がオホーツク海に供給され、その鉄はオホーツク海の中層水として太平洋に供給され、親潮の生物生産を支えるという仮説に基づき、海洋学、陸水学、水文学、農業経済、木材貿易などの専門家がそれぞれの視点から、国境を越えた生態系の保護と生産性の維持を議論した。またPICES(北太平洋における海洋科学に関する政府間機構)には、海洋物理委員会、生物委員会、環境員会、漁業委員会に加え、新たにSection of Human Dimensionが新設され、多くの社会科学者が加わるようになった。同様の傾向は地球環境科学を扱う国際プロジェクトでも見られ、IGBP(地球圏-生物圏国際協同研究計画)は2期において、Human Dimensionに重きを置くことが強調され、2015年からは地球環境科学を扱う4つの大型プロジェクトが統合し、Future Earthとして組織される。もちろんFuture Earthは軸足をHuman Dimensionに移される。
現在の地球システムの中で人類は最大派閥であり、その活動は他の生物の生息圏を侵食し、炭素・窒素循環に影響を与え、気候を変え、これらの影響は我々の生活へフィードバックされ始めている。地球環境研究のゴールは影響を最小限に抑え、我々の生活の持続的発展または維持を図ることを模索することである。炭素循環や気候の問題は理系の問題であるが、生活への影響や社会の維持発展は、理系の手には負えない分野である。このような背景のもと理系と文系は手を結ばざるを得なくなった。20世紀初頭にエジソンは、「我々の科学は人々の生活を豊かにする」と宣言し、20世紀はまさにエジソンの世紀、科学が人類を豊かにした時代であった。しかし、20世紀の終わりくらいから、科学の立場は怪しくなり、現在の地球環境問題に象徴されるように、現代の科学は美しい解決策を与えるというよりは、より悪くない選択肢を提示するといった立ち位置になっている。そしてより悪くない選択のクライテリアは人間が基準となっており、ここが自然科学と社会科学の接点だと思う。たとえば本プロジェクト「新海洋像」においては、直接的にはまだあまり利用されていない外洋の貨幣価値を自然科学的な研究成果から算定することが、自然科学と社会科学を共通の通貨で結ぶ接点である。共通言語としての価値を算定することは大きな意味を持つことになるが、黒倉さんが指摘するように、視点や時代背景によって価値は大きな振れ幅をもつ。通貨レートの変動に呼応して円やドルを売り買いするように、海洋を保護したり開発したりを繰り返すことはできない。30年前(私が学生だった頃)に比べ、海洋のメカニズム、生物多様性や遺伝子配列の持つ意味は大きく理解が進んだが、全容からいえば、ほんの輪郭が見えだしたに過ぎない。現時点での知識を総動員して海洋の価値を算定することには、どうしても抵抗を覚える。価値を算定した途端、それが独り歩きを始め、取り返しのつかない意思決定を導いてしまうのではないかと危惧する。黒倉さんにこのような危惧を伝えると、「心配ない」との返答。本当にそうだろうか?私が参加しているもう一つのプロジェクト「複合生態系」は、沿岸を対象とし、沿岸域の河口域、干潟、アマモ場、褐藻藻場など個生態系の機能を明らかにするとともに、それらが空間配置をもって構成された時の相互作用や集合的な効果を研究し、やはり、目標としては価値を算定することを目的としている。例えば複数の生態系を成長に伴い利用する有用魚類としてスズキがあり、比較的漁獲もあり高級魚の仲間ではあるが、全国の水揚げは1万トン弱、キロ千円と考えれば100億の売り上げにしかならない。100億の売り上げを確保するために河川、河口、砂浜域などの保全を主張することが、本当に勝算のあることだろうか?1995年に日本プランクトン学会で生物多様性に関するシンポジウムを開催し、その取りまとめの文章で、私は「温暖化に代表される地球環境問題は、より良い生活をしたいという人間のエゴであるが、生物多様性は、人間以外の生物にも生存の権利を認める人間のモラルに属する」と言っている。そんな理屈は西洋の人々には通じませんよ、とコンビナーをやっていただいた高橋正征先生から言われたが、何処かで安心しないと研究にも身が入らない。黒倉さん、安心していて良いですか?
文理融合とともに最近よく耳にするのが、意思決定プロセスにおける専門家(研究者)の役割である。福島の事故以来、専門家の権威が失墜したと言われるが、これは、専門家、特に大学の研究者が多様な見解や意見を述べたことが一つの要因であり、これをマスコミ等が御用学者とそれ以外に分類したことでその傾向は助長した。しかし、考えてみると、元来研究者というのは教科書を書き換えるとか、今まで知られていないことを発見するとか、すなわち人と違ったことを唱えることを本位質的に生業としているのであって、専門家だからといってワンボイスにはならないのだが、普通の人々は、世の中には正しいことと正しくないことの2種類しかなく、専門家は正しいことを言うに違いないと考えていたことに、大きな乖離があった。また、古い図式の意思決定プロセスにおける専門家の中立性という側面も、Human Dimensionが軸になると、中立とは何かという問題が難しくなった。役人や議員が専門知識を持つ中立的な専門家の意見を参照し、立法や施策を行うという図式は美しい意思決定メカニズムであったが、現在は役人や政治家同様、我々も、それほど信頼のおける存在ではないらしい。藤垣(2003)によれば、我々専門家は研究ジャーナルの査読システムに起因する信頼性限界を独自(一般とは異なる)に発展させたある意味偏屈な集団であり、我々はその事実に気づかないでいるようだ。彼女は、市民参加型の科学の在り方や、多くのステークホルダーとともに専門家が意思決定にかかわる公共空間モデルなどを紹介しているが、多くの利害関係者が喧々諤々の議論の末、皆が納得することはかなり困難と考えられる。多くの市民を巻き込んで諍いの種を蒔き議論させ妥協点を模索し、それらの過程をポジティブに捉えることが本当に可能だろうか?出来たとしてもあまりに時間がかかりすぎるのではないか?といった疑問をもつ。今風の考え方ではないかもしれないが、人々に専門家がどのような特徴を持った集団なのかを理解してもらい、専門家は人々との接点を意識し中立性という概念を再考し、利害関係者間での議論では到達できない解決策を提示することによって、復権できないかと考えている。
以上雑駁な文章になってしまったが、最後に文理融合のコツを一つだけ。この一年、大学本部でお手伝いをする機会を得たが、その中で17部局の先生方とご一緒した。折角なので、先生方の著書を読んでみることにした。私は理系教員であるが、理系の先生方の書いた本は難攻不落である場合が多い。例えば「金属錯体の光化学」とか「アポトーシス・非アポトーシスの誘導機構から生体機能」というタイトルからある程度想像していただけると思う。これに対して、文系の先生の本は、簡単ではない場合も多いが、内容や意図は追えるし、面白いと思うこともしばしばである。この経験からすると、本プロジェクトに参加している社会科学系の方々は、全体会議などで一日中、専門用語の散りばめられた自然科学系の発表を聞くのはかなり苦痛に満ちた時間ではなかろうかと想像される。一方、溝を埋めるという意味においては、自然科学系の研究者が一歩踏み出し、社会科学系の研究の意図を組み取ることが手っ取り早いと考える。さらに、黒倉さんや八木さんなどの翻訳者、中継者が本プロジェクトにいることは大きな強みと感じる。
引用文献
津田敦(1997)「プランクトンシンポジウム趣旨と報告」1997年度春季プランクトン学会シンポジウム「プランクトン群集の多様性を考える」プランクトン学会報、44、31-33.
藤垣裕子(2003)「専門知と公共性、科学技術社会論の構築へ向けて」東京大学出版会、224p.