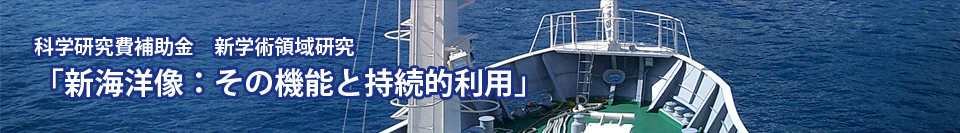連載
「文理融合」のコツ(東京大学大学院農学生命科学研究科 黒倉 壽)
古谷領域代表から、海洋の生態系サービスの価値評価の関する研究グループの代表をするようにと言われたときは、いささか驚いた。価値とは何か、価値がどのように作られるかという問題は、経済学の本質的な問の一つであり、社会心理や哲学とも関連する難問である。そんな難問に経済学の分野では素人にすぎない自分が取り組むことになるとは想像もしなかった。たしかに、生態系サービスの経済価値を計算した過去の論文はいくつかあるのだが、どれもみな、とりあえずありそうな方法で計算したというだけのものであって、価値とは何かという本質的な問を前提には答えていない。簡単に一言でまとめれば、ほとんど何の意味もない論文である。ただし、その影響は大きい。本来、何の意味もないものが、大衆社会の中で情報として拡散し、政治的な意思決定に関わって意味を持ってしまう。最近では、科学にも社会の意思決定に積極的に関わることが求められて、それが「学」の評価であるかのような錯覚を起こしてしまう。水産学や海洋学のように産業や社会との関連を持っている学問分野では、その流れにある程度付き合わざるを得ない。純粋にそれぞれの分野の研究をしたいと思っている研究者にとっては迷惑なことであるかもしれないが、やはり流れには逆らえない。そもそも、価値とは人間にとっての価値であるから、人間の生活や文化が変われば価値基準が変わって価値も代わってしまう。最もよく使われる例は、ダイヤモンドの値段である。値段は価値の表現の一つであり、ダイヤモンドの価値は人間の文化が作り出したもので、その価値は必要性とは関係なく決まっている。そのほか、一杯目のビールと二杯目のビールの価値とか、砂漠の水と洪水域の水の価値とか、様々な例が有り、これらの例について考えるだけでも価値を構成する要素の複雑さを理解することができるだろう。つまり、時間的空間的に一定の絶対的な価値などというものは存在しない。所詮は、今ある社会文化を前提に現在の価値を計算するしかないのであるが、資本財の売買は、将来の利用価値を含めて取引されていることになるので、不確実性を含む将来価値を現時点の価値に割り戻さなければならないという厄介さもある。いずれにしても、こんな複雑なことは素人の手に余る。
それでも、私がその任に起用された理由については、古谷領域代表の意図を推測する以外にないのだが、理系出身の研究者でありながら、社会科学を中心とするいわゆる文系の研究者との付き合いがあり、実際、計量経済学や社会学に分類されるような研究論文に共著者として名を連ねているという点がおそらく評価されたのであろう。私の所属する東京大学大学院農学系研究科・農学国際専攻には、文系の研究室も理系の研究室も所属している。これは、この専攻が、文系理系のような学問業域のとらわれず、社会にある具体的な課題についての問題解決を目的とした研究をすることを標榜しているためである。そのような関係の中で、理系の人間として文化系の研究者とのコミュニケーションが日常的にあるので、理系の人間として文系の科学の言葉を解釈してきた経験を持っていることに期待されたのであろう。いわば通訳である。確かに、そのような経験を比較的多く持っている者の一人であることは認めるが、あまねく、文系の科学の言葉を理系の言葉に翻訳できるという自信があるわけでもない。正直に告白すれば、 文系と言ってのその領域は広く、ある領域についてはかなり自信を持って翻訳できるが、ある領域については全く理解できない。しかし、それでは私にかせられた文系と理系の橋渡しという役を果たせないので、この小論では、私の経験が経験した文系と理系の違いを紹介する。それを通じて、文系の科学を理解するコツのようのものが伝われば幸いである。
1.論文の長さ
理系の研究者が文系の修士論文・博士論文などを読んで、初めに気がつく違いは、論文の長さの違いである。理系では同じ内容であれば、できるだけ短い論文が優れた論文だとする風潮が一般的のように思う。こうした「常識」を前提に文系の論文(すべての分野ではないが、たとえば、社会学、民俗学、法学)を読むと、その長さに驚く。多くの場合、中でも序論の部分が長い。忙しい時に長い序論を読まなければならないのは辛いし、読んでいて眠くなる。副査として参加した学位論文審査で序論を短くしろと注文をつけたら、序論が短いと何を書いているのかわからなくなると叱られた。これに対して、文系の論文では、自然科学の結果にあたる部分の記述が物足りないように感じる。また、あまり出来のよくない論文の場合、考察部分で展開されている議論が、結果にどのように支えられているのか追いきれないことがある。こうなると、読者としては、推察によってその関係を補わなければならず、かなり疲れることになる。反対に、文系の研究者が理系の論文を読むと、背景説明が不十分で、議論をどのように理解すべきなのか戸惑うようである。もちろん、これは一般的な傾向で、文系の中にも「新発見」のようなものがないわけではないし、理系でも長い序論が必要な場合もある。しかし、この一般的な傾向から、理系の研究者は新しく発見されたファクトに興味があって、文系の研究者はそれまでの議論の流れ・歴史に興味があるらしいということが言えそうである。このあたりの感覚の違いは、本領域における生態系サービスの価値評価の議論にも微妙な影響を与えている。すなわち、おそらく理系の参加者は、価値を実存するものとして、定量的に評価することを求めているのだろうが、文系の参加者は、価値はフィクションとして存在するのであって、相対的にも絶対的にも数値そのものには全く意味がないのであって、明らかにすべきものはフィクションの構造だと思っているのではあるまいか。
2.口頭発表
読者諸兄は、口頭発表にあたって原稿を用意されているであろうか。筆者は原稿を用意しない。理由はその時間がないことと面倒だからであるが、いいわけがないわけではない。原稿を用意せずに、聴衆の反応を見ながらその時に浮かんでくる自分の言葉で語りかけたほうが、聴衆が納得する。これは筆者の経験であるが、おそらく、大方の同意を得られるのではないかと思っている。いずれにしても、聴衆が筆者の話そのものに興味を持っていることを前提に聴衆を納得させるために筆者は話している。このやり方が通用しない学会も文系には少なくない。法学系の学会では、あらかじめ作られて提出された原稿を一言半句間違える事無く読み上げる。それならば、原稿参加者全員に郵送すれば良いではないかというのは、他の分野の人間の言うことである。口頭発表が持つ業績としての位置づけは、理系と文系では大きく違っている。特に法学分野では、口頭発表されたということは、定説とは言えないまでも、一定の重きを置かれる説として、位置づけられるということである。口頭発表はそれを確認する重要な儀式である。経済学、社会学、開発学などの学会では、解題と称して、いくつかの関連する発表の前に、「今日の見所」のような、解説が行われる。また、それぞれの発表には、それぞれ討論者というのがついていて、あらかじめ提出された講演原稿を読んで、発表者とのあいだで議論を行う。聴衆はその議論を聞いて、発表の内容を理解するという仕組みになっている。したがって、あらかじめ原稿を作らざるを得ないし、原稿の内容を離れて講演することはできないのである。初めてこの形式で講演した時に、あらかじめ原稿を提出せずに、主催者と討論者から叱られた経験が筆者にはある。おそらく、聴衆は事実ではなく議論に興味があるのだろう。
3.統計処理
文系の論文では、統計的解析はあまり必要がないと思っている理系の研究者がいれば、それは誤りである。もちろん、統計的解析を必要としない分野もあるのだが、計量経済学のような分野では、統計処理を丁寧に行うことが必須である。社会心理学のような分野では、数量化3類や、共分散構造分析のようなマスデーターの統計的な記述方法が頻繁に使われている。統計処理は理系の専売特許ではない。計量経済学の分野では、ある現象を説明する数理モデルをつくり、その妥当性を実際のデーターから検証するということがしばしば行われる。数理モデルはますます複雑化し、非線形モデルへのフィティングの方法も含めて、さまざまな方法がある。しかし、原理的には重回帰分析で行われるように、数理モデルへの適合性がモデルの妥当性の評価となる。正直に告白すると、筆者は時々、理系の論文で何のために統計処理をしているのか、その目的がわからないことがある。不必要ではないかと思うのである。つまり、理系で扱う現象は、原因→結果のように、因果関係が単純で、そこに因果関係が存在することを、あらかじめ了解することが可能な場合に、はたして統計処理が必要なのかと思ってしまうのである。それに比べると、社会現象の因果関係はもう少し複雑で、原因→現象(1)→現象(2)→現象(3)→結果のように、因果関係のプロセスが長く、そこに枝分かれがあったり、影響の小さな多数の要因が存在したり、その要因間に相関があったりする。つまり、因果関係をあらかじめ予想することが不可能であり、多重共線性などを考えると、擬似的な因果関係があたかも真実のように見えてしまうことが少なくない。一方で、ICT技術の進歩により、量販店での商品の売上高のような、マスデーターや、ウェブアンケートの結果なども、たやすく入手可能になった。こうしたデーターを使えば、高い感度で、マイナーな要因の影響も検知できるので、多量のデーターを記述的に表現する技術が必要となり、コンピューターを使った統計処理の技術が発達しているのである。
いずれにしても、統計処理は理系の専売特許ではない。計量経済学や社会心理学では、事実として存在する因果関係を解析しているのであり、その因果関係そのものは実在するファクトである。その因果関係の立証には、理系以上に統計処理が必要である。しかし、その因果関係の成立には、人間社会の文化というフィクションが重要な要素として関係しているのである。
4.まとめ
それ以外にも、学会誌の編集、著書、人間関係など、さらに書きたいこともあったのだが、どうも、同じことを繰り返して主張しているように思えてきた。簡単に要約すれば、理系の人間は、1対1に近い、比較的至近距離の因果関係の成り立ちに興味があり、時間を経ても変わらない、安定した普遍的真理を求めているのに対して、文系の人間は、複雑な因果関係の構造に興味があり、その因果関係には、文化のような虚構が含まれているので、その結論そのものは時間的に安定した普遍的真理では必ずしもない。むしろ、その構造を提示するプロセスに興味があり、その方法の普遍性を求めているだろう。そうだとすれば、良い理系の論文とは、新発見であり、良い文系の論文とは、しっかりした構造的認識である。文系の学会に、派閥争いや人間的対立が多く、理系では多くの場合、研究結果と人格は全く別物と認識されているという違いの理由も、この小論から多少理解していただけるのではないかと思っている。論点を元に戻すと、文理融合とは、理系の人間にとっては、社会に存在する具体的な課題の構造的な認識であり、文系の人間にとっては、観念的議論の前に存在する事実の重さを知ることであろう。